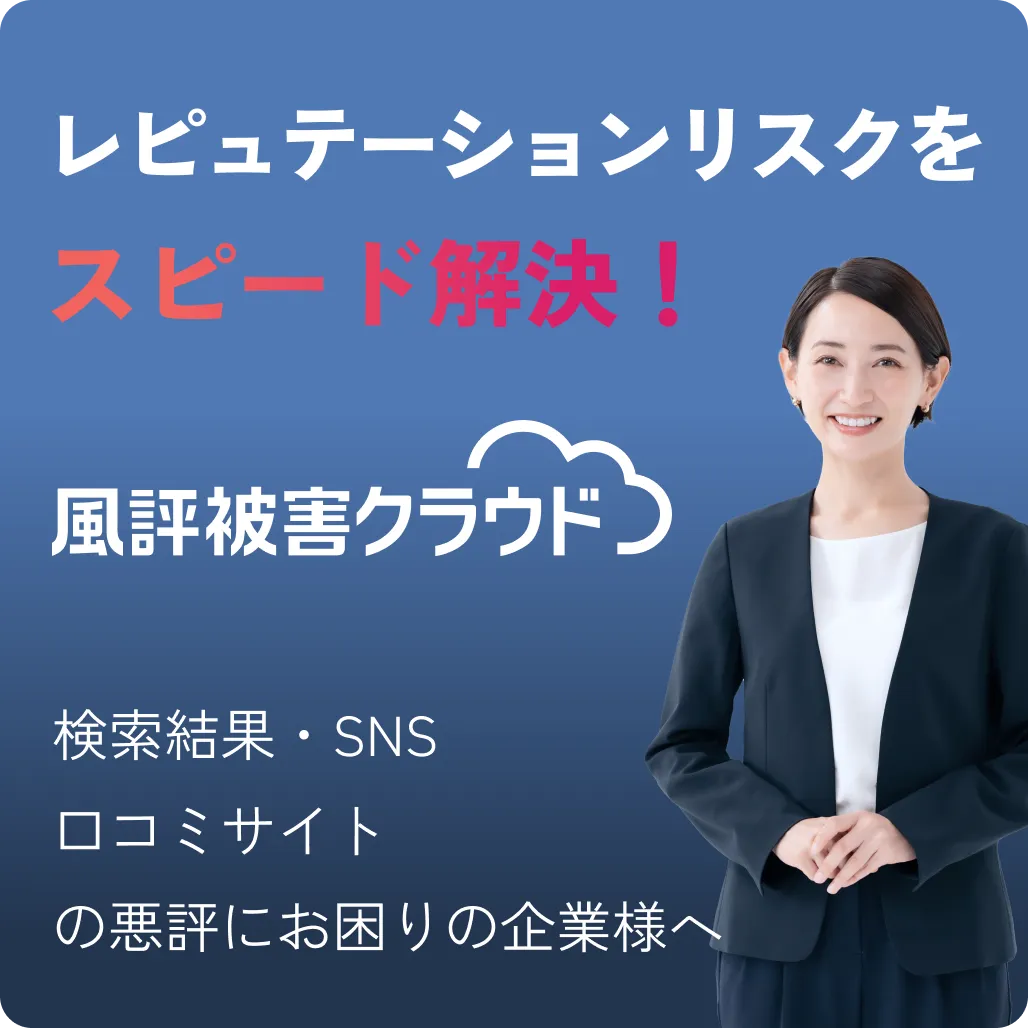誹謗中傷対策とは?誹謗中傷の企業へのリスクと実際の対策方法もご紹介
インターネットが普及し、SNSが発展したことで大きな問題のひとつとなっているのが、SNSなどでの誹謗中傷です。
その対象は個人だけでなく企業であることも多くあり、企業はそれによる被害を出来る限り抑えるためにも誹謗中傷への対策を行うことが重要になるでしょう。
そこで今回は、企業が抱える誹謗中傷のリスクとともに、誹謗中傷対策の方法や誹謗中傷を未然に防ぐための方法などをご紹介していきます。
目次
1. 誹謗中傷対策とは?
誹謗中傷対策とは、個人・団体への非難や名誉を毀損するような情報がインターネット上で発信された際、その被害を抑え、状況を改善に向かわせるための対策を指します。
冒頭でもご紹介したように、誹謗中傷はインターネットが広がり、SNSが発展したことで企業にとっても大きな問題となっています。
総務省においても対策専用サイトを作るなど誹謗中傷への対策には力が入れられており、匿名で誰でも気軽に発信ができ、また高い拡散力を持つSNSが豊富にあることから、企業でも誹謗中傷により企業活動に影響を及ぼしてしまわないよう、対策は急務となっているでしょう。
1-1. そもそも誹謗中傷とは?風評被害との違い
誹謗中傷とはそもそも、個人や団体に向けて根拠のない嘘や噂、悪口などを流布し、名誉を毀損するような行為を指しています。
風評被害とも混同されやすい言葉ですが、誹謗中傷がそういった行為そのものを指しているのに対して、風評被害は根拠のない情報が広がることで生じる経済的・精神的被害を指しており、ひとつの誹謗中傷が原因で風評被害が起こる、といったことも大いにあり得るでしょう。
無料のリスク相談をしてみる
こちらからお気軽にご相談ください。
ブランドクラウドが貴社に合った施策をご提案致します。
2. 企業が誹謗中傷を受けるリスク
企業が誹謗中傷を受けてしまうことで、次のようなリスクが生じます。
2-1. ブランドイメージの低下
まず、誹謗中傷が広がることによるブランドイメージの低下です。
誹謗中傷を目にしたユーザーなどに内容の真偽は分からないため、誤ったネガティブな情報であってもイメージは悪化してしまうでしょう。
2-2. 売上低下や取引停止につながる可能性がある
イメージが低下すれば、顧客離れにつながる、新規顧客獲得のチャンスを失うなど、直接的に売上低下につながってしまう可能性もあります。
また、取引先などからの信頼を失ってしまうことも考えられ、最悪の場合取引や融資の停止にまで追い込まれてしまうかもしれません。
2-3. 人材確保への影響
求職者が応募前に企業の実情を調べることも多く、そういった際に誹謗中傷が目に入ってしまえば、応募の選択肢から外れてしまうことも考えられます。
就職希望者が減少し、人材確保に影響を与えることもあり得るでしょう。
3. 誹謗中傷を受けてしまった場合は?
それでは、もし誹謗中傷を受けてしまった場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。
自社でやるべき対応としては、次のようなものがあります。
- 証拠を確保する
- 削除依頼を出す
- 法的措置をとる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1. 証拠を確保する
まず、重要なのが投稿者が削除してしまう前に証拠を確保しておくことです。
その後の対応において、証拠は必ず役に立つでしょう。
スクリーンショットなどで投稿日時や内容など、問題となる投稿を保存しておきましょう。
3-2. 削除依頼を出す
次に、投稿者や投稿が掲載されているSNSの運営などに対して、削除を求めることです。
投稿をそのまま放置することで情報が広がってしまうのを防ぐために、問題のある投稿を見つけたら削除を要請しましょう。
しかし、削除は運営のポリシーなどによって判断されるため、削除に応じてもらえない場合もあります。
そういった場合には、裁判所に対して仮処分申し立てをするといった手続きが必要になることもあるでしょう。
3-3. 必要があれば法的措置も
投稿内容が悪質な場合や被害を受けた場合には、損害賠償請求や刑事告訴など、法的な措置をとることも可能です。
法的措置を行う場合には相手を特定する必要があるため、投稿者が匿名で分からない場合には、まず発信者情報開示請求を行う必要がありますね。
法的手続きは自社では難しいため、弁護士に相談しましょう。
自社の対策だけでは不安・・・
そんなときはこちらからお気軽にご相談ください。
ブランドクラウドが貴社に合った施策をご提案致します。
4. 誹謗中傷・風評被害を防ぐための対策
誹謗中傷後の対応はもちろん、大きな被害を防ぐために重要なのが、誹謗中傷・風評被害を未然に防ぐための対策です。
誹謗中傷防止の対策としては、
- SNS利用時などのルール策定
- 万が一の際の対応フローの検討
- SNS監視策
などが挙げられます。
4-1. 情報発信時などのルールを定めコンプライアンスを守る
まず、自社の公式アカウントや従業員のSNS利用時のルールやガイドラインを定め、インターネットへの発信はもちろん、すべての業務においてコンプライアンスを徹底して守るということです。
誹謗中傷のきっかけは様々なところにあり、SNS投稿や事業運営に対して揚げ足を取るような投稿がされることもあるでしょう。
少しでもリスクを下げるために、クリーンな運営・発信を意識しておきましょう。
4-2. 誹謗中傷を受けた場合の対応を検討しておく
誹謗中傷を受けた際、対応が遅れてしまったり、対応自体に問題があると、二次被害につながってしまう可能性があります。
そうならないためにも、事前に誹謗中傷を受けた場合には誰がどのようなフローで対応するのか、危機管理体制をしっかりと整えておくのが重要になります。
4-3. SNS監視を行う
誹謗中傷に気づかず放置してしまえば、あっという間に情報が拡散してしまい、風評被害につながるリスクがあります。
できる限りリスクとなる投稿を早く見つけ、迅速に対処するために有効なのが、SNS監視です。
SNS監視は自社でも不可能ではありませんが、目視で行うことになり人員と大きな手間が取られたり、ツールの利用などに専門的な知識が必要になったりと、十分に行うのは難しいでしょう。
本来の業務に集中しながらより効果的に行うために、監視策は専門の対策会社に依頼するのがおすすめです。
専門的なノウハウにより、監視・また発見後の対処まで適切に行ってくれるでしょう。
5. 誹謗中傷・風評被害への対策は「ブランドクラウド」へお任せください

誹謗中傷は企業にとっても大きなリスクのひとつであり、対策が欠かせません。
誹謗中傷やそれによる風評被害への対策を対策会社に依頼したいと考えている方は、ぜひ弊社「ブランドクラウド」にお任せください。
弊社では「風評被害クラウド」というサービスを展開しており、事態を解決に導きます。
「風評被害クラウド」では、AIを用いた風評監視によって悪評などのリスクを早期発見し、誹謗中傷や風評被害といったネガティブな被害を改善・防止するために、変容するインターネットのアルゴリズムに対応できる弊社ならではの施策を行っております。
このような成功率の高い施策や豊富なノウハウにより、インターネット上の幅広いトラブルから効果的に企業活動をお守りするのがブランドクラウドの特徴です。
また、誹謗中傷をはじめネガティブな情報の拡散は非常に速く、インターネット上のあらゆる場所に影響を与える危険性があります。
弊社ブランドクラウドでは、このようなリスクを網羅的に調査できる無料調査も行っております。
まずは一度、お気軽にご相談ください。
風評被害・誹謗中傷対策ならブランドクラウド
こちらからお気軽にご相談ください。
ブランドクラウドなら、最新AI技術で対策成功率94%!
まとめ
今回の記事では、現代での企業活動において注意しなければならない誹謗中傷対策について、その実際の方法や防止策などをご紹介しました。
誹謗中傷にいち早く対策し、風評被害を防ぐためには、SNS監視策など専門対策会社による対策が効果的です。
誹謗中傷にしっかりと備えておきたいという方は、ぜひブランドクラウドをご利用ください。
風評被害クラウドでネット上の
レピュテーションリスクを
スピード解決!
ネットの悪評や風評被害にお悩みの方は
お気軽にご相談ください