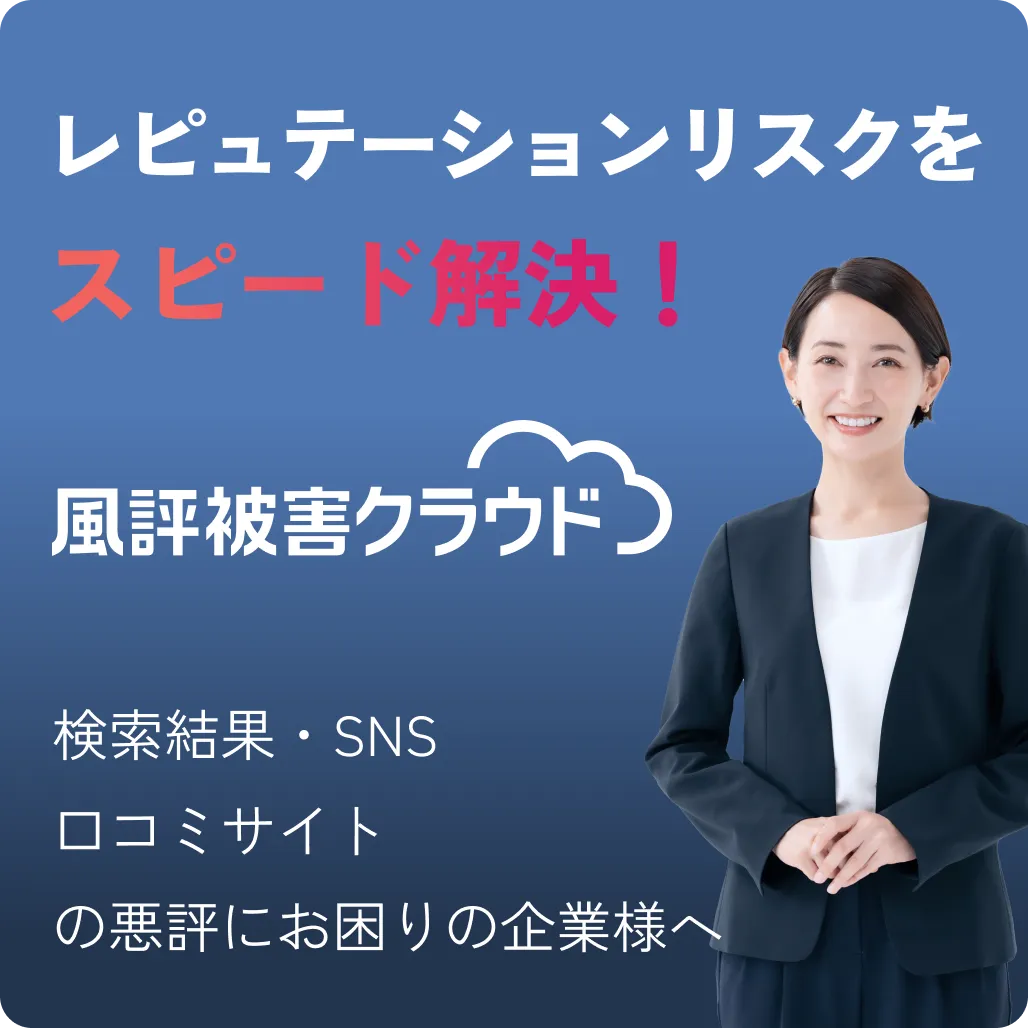なりすましとは?効果的な対策を代表的な手口とともに解説
近年、SNSやメールなど、様々なインターネット上のコミュニケーションツールにおいて、なりすましによる被害が問題視されています。
企業も公式アカウントを運営するなど積極的にビジネスにコミュニケーションツールを活用している現代では、なりすましによる被害は無視できるものではなく、ユーザーからの信頼を保つためにも、対策すべきリスクのひとつと言えるでしょう。
そこで今回は、なりすましの代表的な手口とともに効果的な対策法についてご紹介していきます。
目次
1. なりすましとは?
「なりすまし」とは、他人になりすましてコミュニケーションをとる行為のことを指します。
特にインターネットにおいては、IDやパスワードを不正に利用してSNSを使用するなどして、個人や企業になりすまして詐欺行為やスパム行為、嫌がらせや個人情報の奪取などを行ったりする行為が問題となっているでしょう。
1-1. なりすましが企業に与える悪影響
なりすましのターゲットになるのは個人だけではありません。
例えば不正にログインした企業のSNSから誤情報を拡散し炎上を起こしたり、企業アカウントを装ったアカウントで消費者から金銭や個人情報をだまし取ったりなど、企業などの組織が被害に遭うこともあるでしょう。
そうなれば、セキュリティ面の脆弱性への不安や炎上などによるイメージ低下から顧客や取引先などからの信頼を失ってしまうなど、企業にも大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
2. なりすましの代表的な手口
効果的になりすましへの対策を行うために、まずはなりすましの手法・手口について知っておきましょう。
なりすましの代表的な手口としては、次の3つが挙げられます。
2-1. リスト型
リスト型とは、事前に入手したID・パスワードのリストから、他のサービスへのログインを試みるという手法です。
IDとパスワードを使いまわしているユーザーが多いことを前提としており、データ漏洩や情報流出など、他の事件から得たリストを活用して行われています。
2-2. フィッシング
フィッシングは、企業や銀行といった正規の機関になりすますことで、一般のユーザーから個人情報・認証情報などを盗むという手法です。
例えば金融機関になりすまして偽のアドレスからメールを送り、さらにそこから偽サイトにアクセスさせてログイン情報を抜き取る、といったようなものですね。
フィッシングメッセージは海外から送られていることが多い傾向にあるため、これまでは日本語に違和感があったりと見分けるポイントもあったのですが、近年ではAIが進化していることで見分けるのが難しくなっていると言われています。
企業側では、フォロワーなどに注意喚起を行うといった対策をしておくと良いですね。
2-3. ブルートフォースアタック
ブルートフォースアタックは、一般的に使われやすいパスワードのリストや全文字での組み合わせなど、あらゆる組み合わせの入力を成功するまで試すことで不正にログインを行うといった手法です。
こちらは必ず何度も入力を繰り返す必要があるため、ログインの試行回数制限などでもある程度防止できるでしょう。
3. なりすましを防ぐ!対策法
それでは、企業がなりすましを防止するためにはどのような対処をとればよいのでしょうか。
なりすましを防ぐ対策法としては、次のようなものがあります。
- ID・パスワードは使いまわさない
- 多要素認証を導入する
- 社内での教育・研修
- モニタリング
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1. ID・パスワードは使いまわさない
まず、基本ですが複数のサービスでID・パスワードは使いまわさないことです。
使いまわしをしていると、どこかのサービスから情報が漏れた際に他のサイトにも不正アクセスされてしまう事態を引き起こしてしまいます。
できるだけ複雑で、サイトごとに異なるID・パスワードを設定しましょう。
定期的にパスワードを変更するといった対策も有効ですね。
3-2. 多要素認証を導入する
多要素認証とは、ID・パスワードだけでなく、例えば秘密の質問やICカードなどの情報、指紋・顔認証などの生体情報など、複数の情報を組み合わせて本人確認を行うセキュリティの手法です。
もしもID・パスワードが流出しても他の情報が合わせて必要になるため、不正アクセスを防ぐことができるでしょう。
3-3. 社内での教育・研修
企業全体でなりすましへの対策を行うため、従業員に対しても情報セキュリティに関する教育・研修を行いましょう。
ご紹介したようななりすましの手口や実際の被害からなりすまし被害が起きた場合企業にどのようなリスクがあるのかを知っておくことで、セキュリティ意識を高めることができます。
情報漏洩の原因としてヒューマンエラーも多くあると言われるため、従業員1人1人がセキュリティ意識を持つことは重要です。
3-4. モニタリング
SNS上を定期的にモニタリングし、企業のなりすましが行われていないか確認するのも対策のひとつです。
ソーシャルモニタリングは得た情報をマーケティングに活用するという目的で行われることもありますが、なりすましや炎上の火種となる投稿を発見し、できる限り早めに対処するなど、リスクへの対策としても非常に有効です。
モニタリングは目視などで自社でも行うことができますが、より効果的に手間なく行うために、専門対策会社に依頼するのもおすすめですね。
専門対策会社によるモニタリングで、なりすましの対策をしたい!
そんなときはこちらからお気軽にご相談ください。
ブランドクラウドが貴社に合った施策をご提案致します。
4. なりすましによるトラブル・リスクは「ブランドクラウド」にお任せください

SNS・インターネットは企業や店舗にとって欠かせないツールのひとつでもありますが、なりすましをはじめ、多くのリスクがあることも否定できません。
現代に多いインターネットのトラブルに備えたいと考えている方は、ぜひ弊社「ブランドクラウド」にお任せください。
弊社では、アメリカで統計的手法を用いて構築された体系的なアプローチによって行われるブランドリフティングサービスや、風評被害が起こるリスクに対して根本からの対策を行う「風評被害クラウド」などのサービスをご提供しております。
企業・製品のブランディングや評判の改善、認知度向上などにつながるポジティブな施策はもちろん、誹謗中傷や風評被害などのネガティブな被害を改善・防止するために、変容するインターネットのアルゴリズムに対応できる弊社ならではの施策を行っております。
このような成功率の高い施策や豊富なノウハウにより、インターネット上の幅広いトラブルから効果的に企業活動をお守りするのがブランドクラウドの特徴です。
また、ネガティブな情報は非常に速く拡散するため、検索結果などインターネット上の他の場所にまで影響が広がってしまっている可能性もあります。
弊社ブランドクラウドでは、このような様々なレピュテーションリスクを網羅的に調査できる無料調査も行っております。
まずはぜひ一度、お気軽にご相談ください。
インターネットトラブルを避けたい!
こちらからお気軽にご相談ください。
ブランドクラウドなら、最新AI技術で対策成功率94%!
まとめ
今回の記事では、近年被害が増加しているなりすましに関して、なりすましが企業に及ぼす影響や代表的な手口、企業が行うべき対処法などを詳しくご紹介しました。
SNSなどコミュニケーションツールが発達しており、業務上でも欠かせない現代では、なりすましは個人だけでなく企業にとっても大きなリスクのひとつです。
モニタリングなど効果的な対策を行いたいと考えている方は、ぜひブランドクラウドにお任せください。
風評被害クラウドでネット上の
レピュテーションリスクを
スピード解決!
ネットの悪評や風評被害にお悩みの方は
お気軽にご相談ください